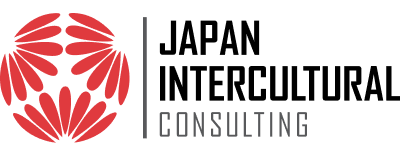2012年10月24日 オリンパス事件が示したガバナンスの新たな教訓
オリンパスの粉飾決算事件の初公判が開かれ、菊川剛元社長が損失隠しの起訴内容を認めました。また、ソニーがオリンパス株式の約11%を取得することに合意し、オリンパスの未来は確保されました。これをもって、会社が崩壊して多数の社員が路頭に迷うという、菊川氏本人が恐れた最悪の事態は回避されながらも、正義が下されつつあるように見受けられます。
オリンパスのマイケル・ウッドフォード前社長が回顧録として記した事件の全容を読むにつけ、私は、何か別の問題解決方法がなかったものかと考えずにはいられません。本に綴られたなかでも決定的な瞬間は、ウッドフォード氏の支持者であった菊川氏が、粉飾の責任を受け入れて辞職するよう事実上迫られていることに気付き、「マイケル、私のことが憎いか?」と尋ねた瞬間です。
ウッドフォード氏にとって、この問いは、理解を超えるものでした。菊川氏に対する追及は個人的なものではなく、役員として当然の務めと考えていたからです。起きた出来事を透明にし、罪を犯した者の責任を問うことは、立場を任された者の任務の一部でしかなかったのです。
けれども、菊川氏にとっては、粉飾が会社を救うための窮余の策であり、そこに私利私欲が介在していなかったことは、私にも想像がつきます。菊川氏には、会社の運命に対する役員としての務めと従業員に対する責任を、自分自身の運命と切り離すことができなかったのです。このため、自分の行動に対する攻撃は自分という人間に対する攻撃であって、しかも会社が存続できるかどうかなど気にかけていないかのように見える相手からの攻撃であると思えたのでした。
この点について、ウッドフォード氏は、オリンパスの存続を誠心誠意、気にかけていることを何よりも明らかにしています。ただし、告発、処罰、贖罪という過程こそが、会社の再生を可能にすると信じていました。アングロサクソン文化圏の資本主義世界で生まれ育った多くのエグゼクティブは、これに似たマインドセットを持っています。すなわち、自分が経営する会社から自分自身を切り離し、客観的に眺めることができるのです。
しかし、これには短所もあります。他人の築いてきた会社に乗り込んで、大胆な再編を行い、過去につながっている一部の人々を掃討して、自分の「てか」(ほぼ必ずと言っていいほど男性)を地位に就けることで、必要な結果を出そうとする傾向があることです。数字さえ良ければ株主は幸せで、犠牲者は落伍するけれども、どこかまた別の会社で新たなスタートを切れる、という考え方をしがちなのです。
これは、日本での現実とは異なります。そして、オリンパス事件を単なるコーポレート・ガバナンスの問題ケースとして片付けているだけでは、日本にもコーポレート・ガバナンスの基準があり、それを実践することが可能かつ義務であるという事実を見落としています。しかも、日本の企業環境は、欧米のそれと同じぐらい複雑化しています。残業や多様性についての法規はもちろん、外国人エグゼクティブが無視しては落とし穴にはまり込む「パワー・ハラスメント」を統制する規則も存在しています。
外国人エグゼクティブが日本で挫折した事例はあまりにも多く散在しています。これを見れば、日本企業はもはや、単に外国人エグゼクティブを指名すれば何やら魔法のように事業がグローバル化すると願うわけにはいかないでしょう。外国人エグゼクティブには、強力なサポートと指導が必要です。日本の役員会の仕組みについてのトレーニングから、日本人従業員の管理経験がある先輩によるコーチングまで、彼らが崩壊を巻き起こさずに好ましい変化をもたらせるようになるための手段が講じられなければなりません。